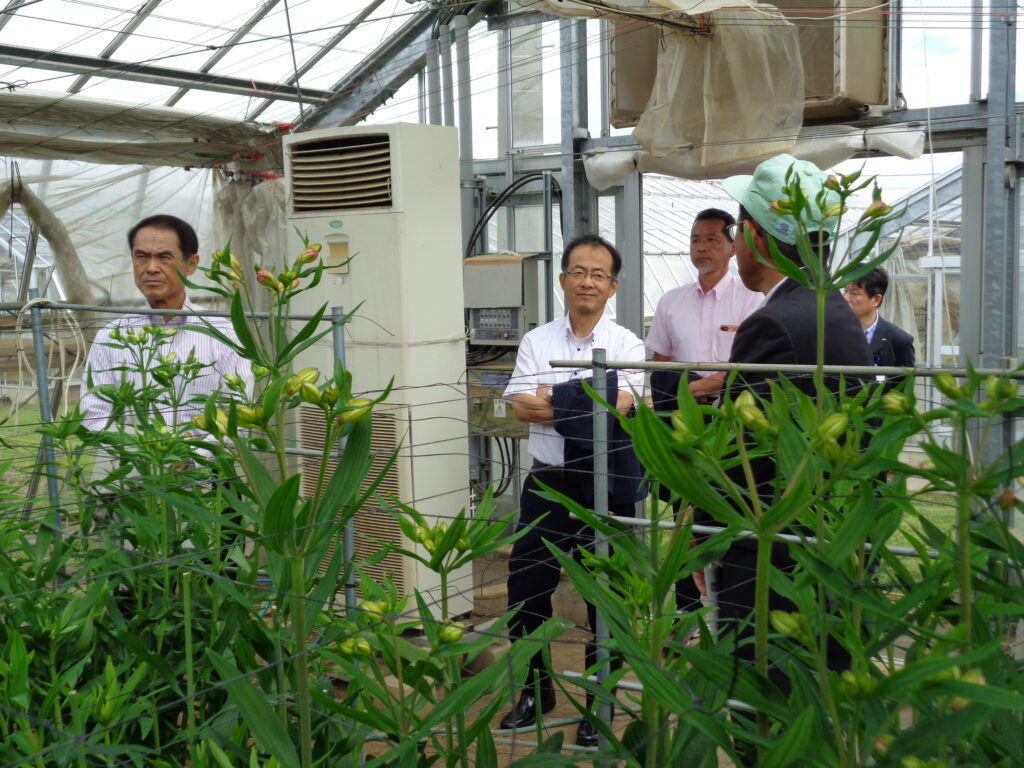6月19日(木)に、県議会6月定例会が開会しました。
19日には知事から議案が提出され、提案説明がありました。
知事は、提案説明の中で県内の出生数が過去最低を更新したことに触れ、「固定的な性別役割分担意識の見直しなど、若者や女性に選ばれる寛容で多様性を尊重する社会の実現に向け、取組を進める。」と発言しました。
このことについては、私が従来から一般質問などで主張していることと全く同じ趣旨であり、大いに賛同するものです。
議案は、総額38億5,700万円の一般会計補正予算案など20議案です。
一般会計補正予算案のうち主なものは、次のとおりです。
・ 「物価高騰・米国関税措置支援」の実行
・ 医療供給体制の整備(診療所の継承・開業支援など)
・ しあわせ信州農福プロジェクトの実施
・ 教育環境の整備(高校再編整備など)
・ 地域公共交通の維持・活性化
議案については、6月30日(月)から7月2日(水)に開催される各常任委員会で審議されます。私は環境・文教委員として補正予算等の議案の審議に参加し、質問や提案を行います。
会期は16日間で、7月4日(金)に閉会します。