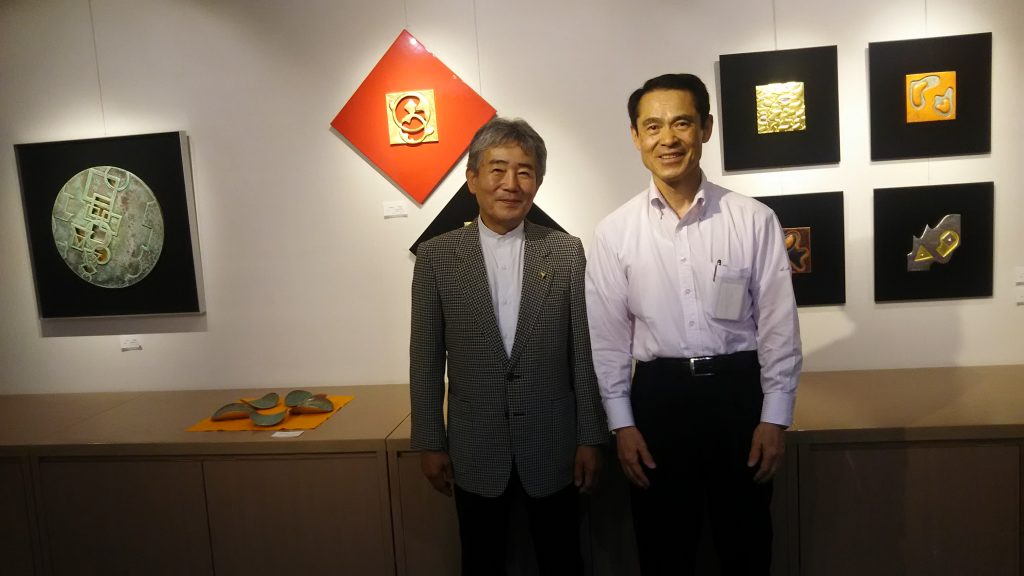7月27日(木)・28日(金)の2日間にわたり、県議会文教・企業委員会の現地調査が行われ、委員として参加しました。
今回は、東北信地域の県現地機関や委員会関連の事業実施箇所などを調査しました。
事業実施箇所の概要について、5回に分けて報告します。
第1回目は、佐久市にある県立望月高校です。
調査に入る前に、「佐久市・もちづき教育未来会議・望月高校同窓会」から「望月高校の存続に関する陳情書」が議会文教・企業委員長あてに提出されました。
県では、現在第1期の高校再編計画を実施中(平成29年度まで)ですが、県の基準に該当すると再編の対象になります。
基準によると、2年連続で全校生徒数が160人以下の高校が対象になり、望月高校は2年連続で156人であったため、基準に該当します。
この基準は、少子化が進み学校規模が小さくなった場合に、生徒への学習が十分には保障できなくなることから、一定規模以下の高校を再編するために設けられたものです。
再編対象になった場合、分校化・他校との統合・募集停止の中から選択することになります。
地域の皆さんには、「高校が無くなることは地域の衰退につながる」との懸念の声があります。
一方、「少子化が進めば、単独で存続してもいずれは立ち行かなくなる。分校化した上で、特色ある授業を進めることを考える方が現実的」との声もあります。
議会としても、地域の思いや実態、今後の地域の高校生にとってどうあるべきかなどについて総合的に検討しますが、難しい判断を迫られます。